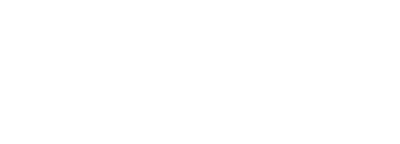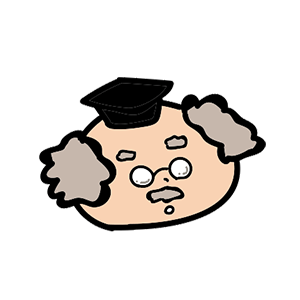
二人とも、金魚すくいは好きかね?



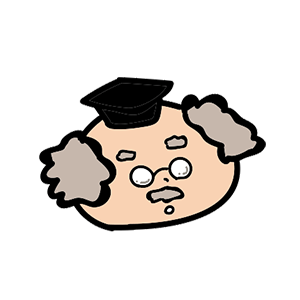
金魚は飼育方法を誤るとすぐに死んでしまうが、もともとそんなに弱い種類じゃぁないんじゃよ。
今回は金魚すくいでとった金魚を飼うために必要な設備や知識、注意点についてご説明していきます!
もくじ
金魚すくいに使われる金魚

お祭りにいる金魚はどんな種類の金魚なのでしょうか。
水槽には赤くて小さい金魚や黒い眼の出っ張った金魚などがいるイメージです。
和金
金魚すくいの定番の金魚は、「和金」と呼ばれる種類です。別名「子赤」とも呼ばれています
とても丈夫で飼いやすい金魚の一種です。
和金は家庭でも飼育しやすく、泳ぐのもとっても上手です。そのため金魚すくいの難易度も上がりますね(笑)
金魚すくいでもらえる和金の体長は3~4cm程ですが、上手に育てれば20cm程にまで成長することもあるでしょう。
寿命は5~10年といわれています。
出目金
和金に混ざっていて目が飛び出しているのが特徴の金魚は「出目金」です。
掬った時は小さいものの、育てれば15~20cmにまで成長させることが可能です。
寿命は平均5~6年ですが、丁寧に管理すれば7~8年、長いものでは10年生きるものもいます。
まとめ
「金魚すくいの金魚って寿命が短い、安い金魚なんじゃない?」
と思っている方も多いと思います。
しかし、結構寿命が長い種類の金魚が使われているんです。
和金や出目金の寿命を左右する大きな要因は、何処から連れてきたかよりも今居る環境が最適な環境かどうかが重要になってきます。
連れ帰った金魚に対して最初に行うこと
金魚すくいで使われる金魚は、商品として失格と判断された個体で、最初から弱っていたり、病気を持っていたり、ケガをしていたり、見栄えや体型がよくなかったりと最初からハンデがあるもの、
または、大型魚のエサ用で生まれて3カ月程度の金魚の子供です。
いずれにしても、狭い水槽で温度調整もなく、酸素も薄い中追いかけまわされた金魚はかなり弱っています。
また病気にかかっている可能性が高いので金魚が養生できる環境を作る必要があります。
金魚を養生する手順
①できる限り大きな入れ物にカルキ抜きした水を用意します。
斑点やケガが見うけられたり、動きが鈍いなどの金魚は別隔離の入れ物を用意しましょう。
②次は水温調整です。
袋のまま、まずは水槽の上に浮かべ、温度を徐々に慣らしていきます。金魚の適温は15~28度です。
温度が同じくらいになったら放します。この時に感染防止のため異常がみられる金魚は分けましょう。
③次に金魚の浸透圧と同じ0.5%の塩水にします。
すぐに塩を入れず徐々に0.5%まで上げていきましょう。
④3日~1週間断食させます。食事をするのにもエネルギーを必要とするので、弱っているときに食事を与えても消化不良を起こすだけです。
フンが出たら塩を入れて水を交換してください。
⑤水槽に入れます。
この時点で元気に泳いでいれば山は越えたので、水槽にうつしましょう。
元々水槽に別の魚がいる場合は殺菌のため唐辛子を1つ水槽の中に入れると良いでしょう。
カルキ抜きした水の用意がないときの緊急対応策
「子供が金魚をとってきてしまった!準備してない!」
など
カルキを抜いた水が準備でき定ていない時の緊急対応策を紹介します。
カルキとは塩素のことなので、ビタミンCでも分解が可能です。
レモン飴やレモン汁を数滴入れて代用できます。
家で金魚を育てるために必要なもの

家でお祭りでとってきた金魚を飼育するためにはある程度準備が必要です。
金魚を飼うために必要なものは主に4つあります。
・エアポンプ
・エサ
・ろ過装置
水槽の準備
金魚のサイズや数に合わせた水槽が必要になります。
小さい魚が一匹増えたって水槽の大きさには関係ないだろうと思うかもしれないですが、とても重要なんです。
小さい水槽に多くの金魚を詰め込んでしまうとストレスが溜まってしまいます。
一般的には最低でも体長1cmの金魚で1リットル以上の水が必要だと言われています。
金魚すくいでもらえる金魚が3センチとして、3匹飼うとすれば9リットル以上は最低でも必要です。
意外と多いですよね。
さらに大きく育てたいのであれば大きな水槽にする必要があります。
先を見越して大きめのサイズの水槽を買った方がいいかもしれません。
小さな水槽は運動不足・酸素不足・水質悪化になりやすいです。その分、病気になる可能性も高くなります。
金魚にとっては水槽が大きいにこしたことはありません。しかし、大きい水槽が難しい場合は細やかな管理が大切になります。
エアポンプの準備
金魚は他の魚同様、水中の酸素を吸って生活しています。
そのため、限られた水槽内で呼吸をしていると、酸素がなくなって呼吸が苦しくなってしまいます。
口をパクパクしているのはお腹がすいているのではなく、息が苦しいというサインなので金魚のため、水に酸素を送るエアポンプを用意してあげましょう。
エアポンプによって水に酸素を送ることはできますが、エサやフンで水は汚れます。
もちろん水は毎日変えてあげましょう。
エサの準備
当たり前ですが、エサを食べる量は基本的に体重に比例して多くなります。
また、大きな水槽で飼育していると良く運動するため、たくさん餌を食べるでしょう。
あげる回数の目安は
春から夏にかけては1日に2~4回、
秋から冬にかけては1~2日に1回
量としては2,3分で食べ終わる量が適切なので、様子を見ながら丁度いい量を見つけてあげましょう。
残ったエサは水の汚れの原因になるので、網などで取り除いてあげましょう。
こちらは大容量なお徳用のエサです。
ろ過装置の準備
絶対に必要だというわけではありませんが、ろ過装置はあると便利です。
基本的に毎日水を変えることが望ましいとされていますが、ろ過装置は水が汚れるスピードを遅らせてくれます。
目に見えるゴミを濾しとってくれたり、排せつ物などの有害物質を無害化してくれます。
グッズをそろえるのが大変な場合、セット商品なども販売しているのでご覧になってみてください!
これ一つで簡単に飼い始めることができるとても便利なセットです。
長生きさせたいなら何をすればいいの?

金魚を長生きさせるためには更に細やかなことに注意する必要があります。
水を交換して清潔さを保つ
水換えはろ過装置があれば1~2週間に1回で大丈夫でしょう。水替えは1回にすべてではなく半分ずつ、3分の1ずつで替えても問題ありません。
交換の際に気を付けるべきことを記載していきます。
①カルキ抜き
カルキを抜かないと、金魚を苦しめることになります。
魚は水中の酸素を取り入れます。そのため、水道水に含まれる塩素が入った水で金魚が呼吸をすると、水に含まれる塩素がエラに入り、細胞を破壊します。破壊された細胞は長年復活できないので、そのまま死んでしまいます。
専用の機械を使わずとも日当たりのいい場所に水道水を1日置いておけばカルキが抜けるのでペットボトルなどでも簡単にカルキ抜きが行えます。常に補充しておくようにしましょう。
これらの手順が手間に感じる人はカルキ抜きを使ってもいいです。
②水温
金魚に適した水温は15~28度です。室内で飼育していれば基本問題ありません。
水温が30℃以上になると日本古来の淡水魚に取っては良くない環境なので夏の暑い日は室温に気を使ってあげましょう。
強力なろ過装置を使う
長生きさせたい場合、目に見えない毒素までしっかりと取り除いてあげることが重要になります。
ろ過ができていないかどうかはニオイも基準になります。フィルターがうまく機能していなかったとき、毒素は嫌なにおいを出します。
顔を近づけても常に無臭であるくらいにきれいな状態を維持することも重要です。
ろ過装置には外部式フィルター、上部式フィルター、底面式フィルターなど様々な種類がありますが、おすすめは成長して水槽サイズを変えても使える外部式フィルターです。 ジェックス 簡単ラクラクパワーフィルター M
ただ、外部式フィルターは少しお値段が高いので、金魚が少なければ投げ込み式や外掛式でもいいと思います。
水槽は大きいものを用意する
必要サイズよりも大きめな水槽を用意することが望ましいです。
大きさや数に対して水槽が小さいと毒素濃度が上がりやすくなってしまうためです。
味噌汁を作るときに一人分なら大匙一杯分の味噌でちょうどよくても、5人分作るとしたら同じ大匙1杯では薄くなるのと同じ原理です。
大きい水槽であればあるほどきれいな水槽を保ちやすくなるので寿命もおのずと延びてきます。
長生きさせるのであれば大きな水槽を用意してあげましょう。
まとめ

金魚すくいで傷ついた金魚を養生し山場を越えれば、お祭りの金魚を長生きさせ、成長させるのは育て方次第です。
300円の金魚すくいで捕まえた金魚だからと考えず、育てる準備をして元気に育ててあげましょう!

丁寧に飼育すればちゃんと元気になるんだね。

今年のお祭りでは金魚すくいやってみよっと!